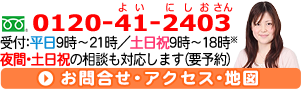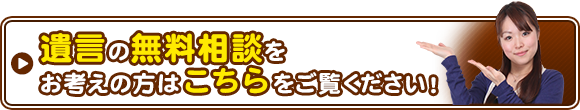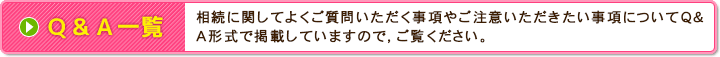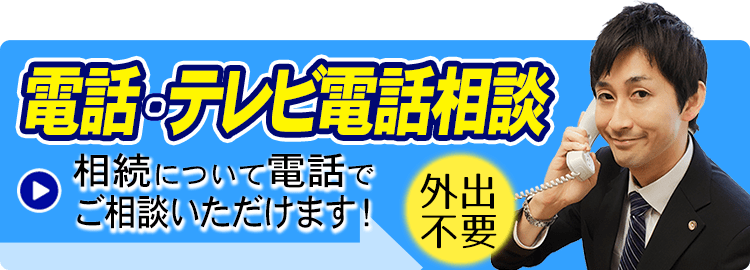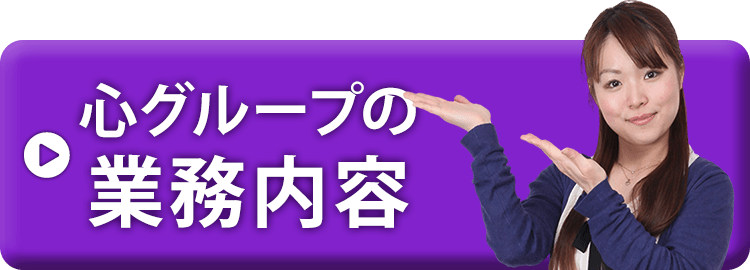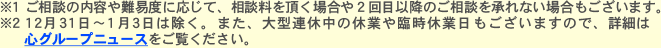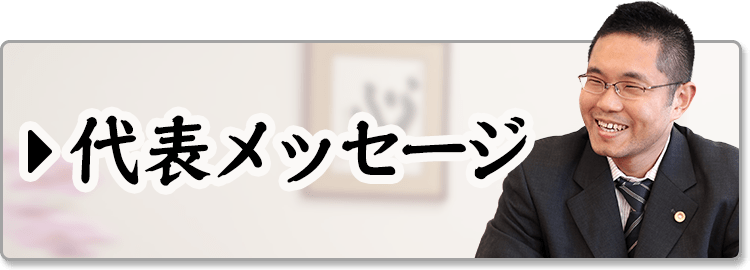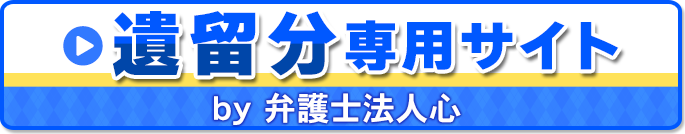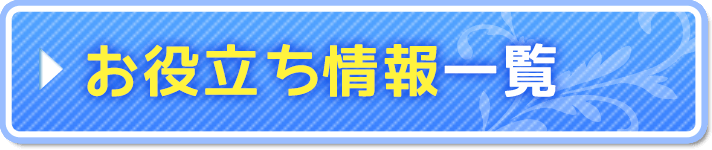遺言がある場合の相続の進め方
1 遺言の種類を確認する
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
一般的によく利用される遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
どの種類の遺言かによって、必要な手続きや進め方が変わります。
遺言が発見された場合、まずはどの種類の遺言であるかを確認することがポイントです。
2 検認手続き
自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言が発見された場合、検認という手続きを行う必要があります。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申立てを行わなければなりません。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
検認手続きでは、申立人、出席した相続人、裁判所の職員が立ち会います。
また、検認手続きでは、遺言書が開封され、遺言の内容が読み上げられます。
検認が終わると、検認済証明書が作成されます。
検認済証明書は預金の解約や不動産の登記名義の変更を行うのに必要となりますので、交付を受けるようにし、交付を受けた後は大切に保管するようにしてください。
3 遺言の内容を実現する
自筆証書遺言か秘密証書遺言で検認手続きが終わった場合、遺言に書いてあることを実現していくことになります。
公正証書遺言の場合には、検認手続きは必要ありませんので、遺言を見つけ次第、遺言内容を実現することになります。
遺言に遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が中心となって、相続手続きを進めていきます。
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合には、相続人自身で遺言書を使用して相続手続きを進めていくことになります。
もっとも、相続人同士で誰が相続手続きをするかで揉めてしまうような場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
遺言書がある場合、相続手続きをするにも専門的な知識が必要となりますので、遺言書が見つかった場合には専門家に相談されることをおすすめします。
お役立ち情報トップへ 銀行口座の相続手続きに必要となる書類と集め方