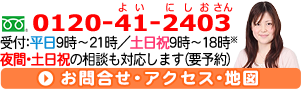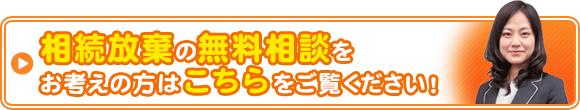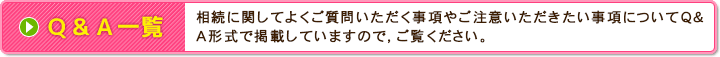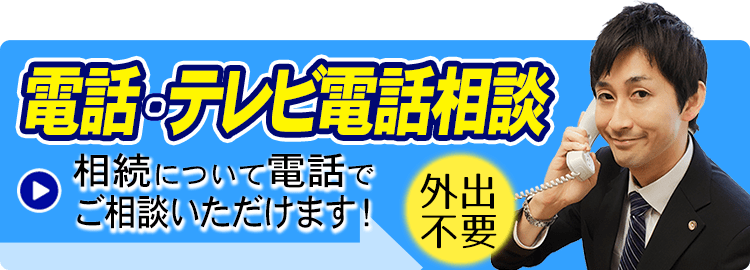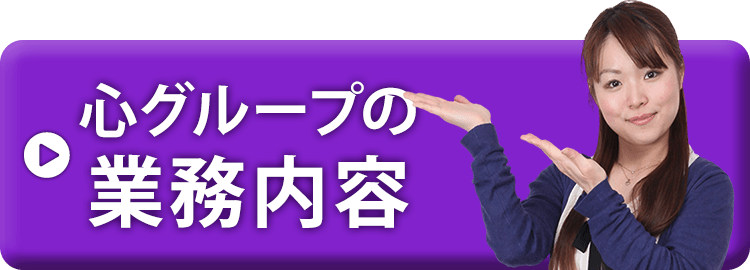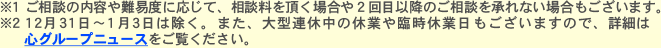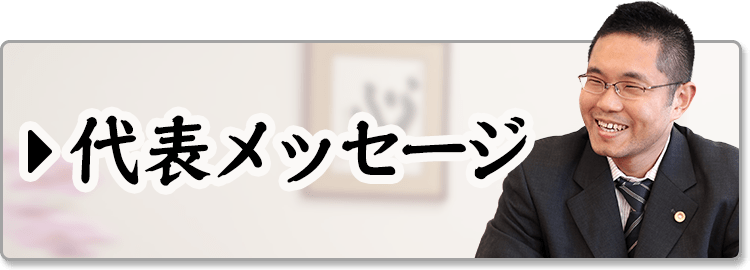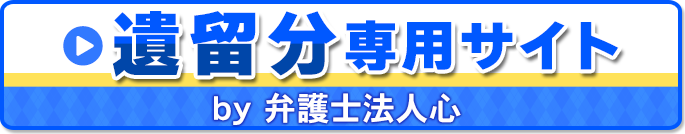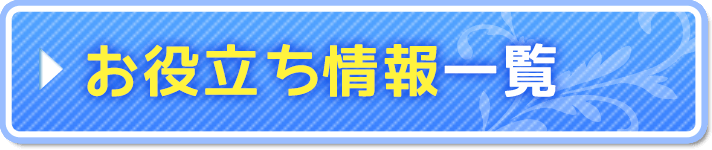相続放棄の理由と申述書への書き方
1 相続放棄の理由
相続放棄の理由としては、債務を相続したくないという場合や、被相続人と関係が疎遠であったために相続をしたくないといった理由が考えられます。
裁判所所定の書式を使用して相続放棄の申述をする場合、書式の中に「放棄の理由」という欄があり、相続放棄の理由を選択する形式になっていますので、当てはまる理由の選択肢に○をつけて提出します。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
2 相続の開始を知った日について
相続放棄では、相続人が相続の開始を知った日が重要となり、申述書の記入にも関わってきます。
具体的には、相続人が「自己のために相続があったことを知った時」から3か月以内(この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。)に、相続放棄をするか決めなければならないとされています(民法第915条)。
ここでいう「自己のために相続があったことを知った時」は、①相続開始の原因事実を知り、②そのために自己が相続人になったことを知った時とされています。
申述書では、申述者が、相続開始と自分が相続人となったことを知った経緯について記載する必要があります。
裁判所所定の書式を使用して相続放棄の申述をする場合、相続開始を知った日について記載する欄がありますので、その欄に相続開始を知った具体的な日付を記載して提出することになります。
当然、熟慮期間内に申述書も提出しなければならないため、注意が必要です。
3 相続財産について
裁判所所定の書式には、遺産の内容を記載する欄があります。
この欄には、プラスの財産とマイナスの財産のそれぞれについて分かる範囲で記載します。
ここで注意が必要なのは、相続財産を処分してしまった場合、その時点で相続放棄をすることができなくなるという点です。
相続財産の処分をした場合、相続人は黙示的に相続することを受け入れたといえます。
また、第三者から見ても財産を処分したような場合には、単純承認があったと信じるのが通常といえます。
そこで、民法では、相続人が相続財産の処分をしたような場合には、当該相続人が単純承認をしたものとみなすとされています。
そのため、相続放棄の理由を記載するにあたり、相続財産を処分していないかについて注意する必要があります。
銀行口座の相続手続きに必要となる書類と集め方 遺産相続で財産が家しかない場合、どうやって遺産分割するか