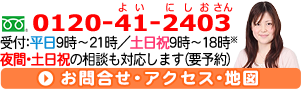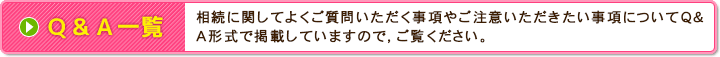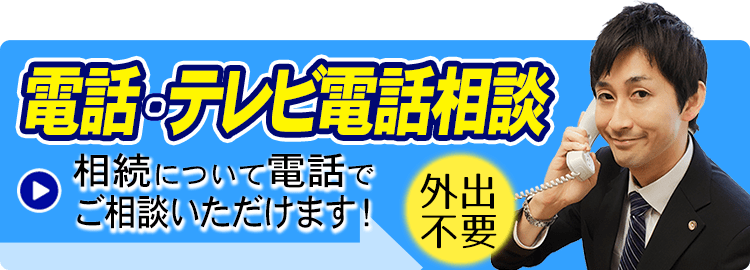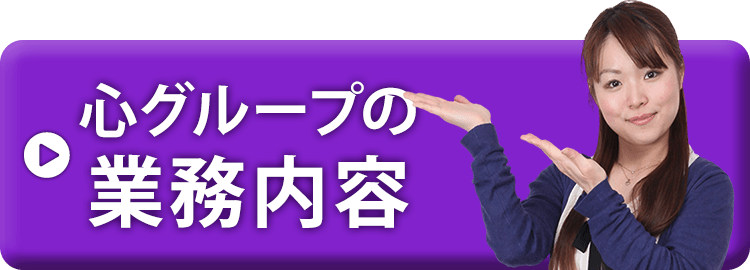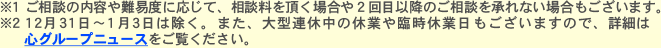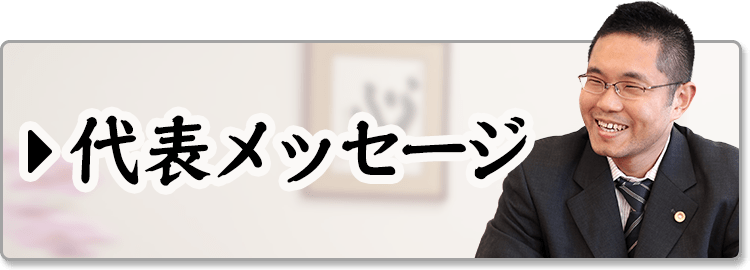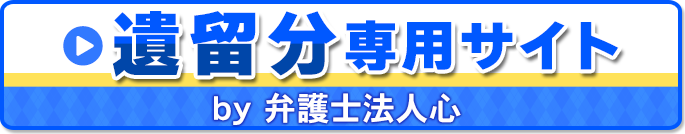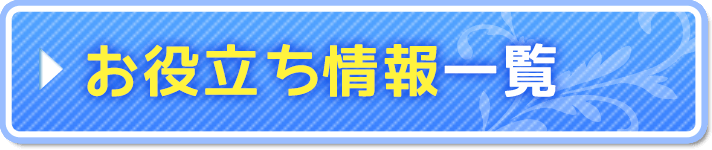銀行口座の相続手続きに必要となる書類と集め方
1 口座名義人が亡くなると銀行口座は凍結される
被相続人が亡くなったことを銀行が知ったときは、銀行は被相続人の口座を凍結します。
そのため、その後は、相続手続きをしないと当該口座の使用ができなくなります。
また、口座の相続手続きをすると言っても、通常銀行は口座名義を被相続人から相続人へ変更をすることはしないので、相続人が被相続人の口座から預金を引き出し、振替をする手続きになります。
2 被相続人の口座を特定の相続人が相続するに至った手続き
特定の相続人が被相続人の特定の銀行口座を取得するのは、①遺言による場合、②遺産分割協議による場合、③家庭裁判所の調停、審判による場合があります。
他に、相続人が決まる前に被相続人の口座から相続人が預金を引き出せる場合もありますが、今回は言及しません。
それぞれの取得に至った手続きによって必要な書類が異なるので、各場合に分けて説明します。
それぞれの場合に記載したものの他に、通常、各金融機関独自の届出書類があります。
通常、その書類には、印鑑証明書が必要な方の署名と実印の押印が必要になります。
3 遺言による場合
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類があります。
自筆証書遺言については法務局保管制度を利用する場合と利用しない場合があり、自筆証書で法務局保管制度を利用しない場合と秘密証書遺言の場合は、裁判所の検認を受ける必要があります。
検認手続きが必要である遺言の場合、必要な書類は概ね以下のとおりです。
①遺言書
②検認調書あるいは検認済証明書
③被相続人の死亡の事実が反映された戸籍謄本(全部事項証明書)あるいは除籍謄本(全部事項証明書)
④預金を相続する相続人の印鑑証明書
遺言執行者による場合は遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者が遺言ではなく家庭裁判所で選任されたときは選任審判書謄本も必要)
検認手続きが不要である遺言の場合、必要な書類は概ね上記の②以外の書類となります。
4 遺産分割協議による場合
遺産分割協議による場合、必要な書類は概ね以下のとおりです。
①遺産分割協議書(全ての法定相続人の署名と実印による押印があるもの)
②被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本(全部事項証明書)※改正原戸籍謄本、除籍謄本などが必要になる場合もある
③相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
④相続人全員の印鑑証明書
5 家庭裁判所の調停、審判による場合
家庭裁判所の調停、審判による場合、必要な書類は概ね以下のとおりです。
①調停調書謄本(調停の場合)、審判書謄本(審判の場合、確定表示がない場合は審判確定証明書も要)
6 以上に当てはまらない場合(共同相続)
①被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本(全部事項証明書)
※改正原戸籍謄本、除籍謄本などが必要になる場合もある
②相続人全員の印鑑証明書
7 その他の書類
上記以外にも、各金融機関により別の書類を求められる可能性があるため、まずはそれぞれの金融機関に確認をしてください。
相続手続きをするにあたって、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要になる場面は多いですが、これらの書類を法務局に提出するとき等に法定相続一覧図を提出し、これに認証文を付した写しを交付してもらえば、以後の手続きで被相続人の出生から死亡までの連続する謄本に替えて提出できる場合が多いです。
8 それぞれの書類の集め方
上記の内で集め方に迷うものは被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本等だと思います。
これらを集めるには、まず被相続人の最後の戸籍地の市区町村で同一の管轄内での移動したすべての戸籍謄本等を出してもらい、出生まで辿り着けなかった場合は、その中の一番古い戸籍からその前の戸籍地を確認し、そこの市区町村にて戸籍謄本等を取得するということを出生に遡るまで繰り返します。
これらを申請できるのは、被相続人の配偶者か直系の親族に限られるので、それ以外の方が申請するときは、事前に委任状を配偶者や直系の親族からもらい、本人を確認できる運転免許証やマイナンバーカードなどとともに持参する必要があります。
遺言がある場合の相続の進め方 相続放棄の理由と申述書への書き方